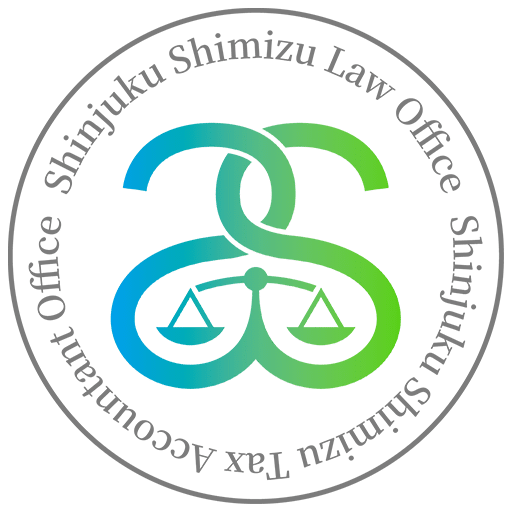令和4年4月1日、民法上成年となる年齢が18歳となりました。
元々、平成30年の民法改正以前は、成年となる年齢は20歳でした。
近年、公職選挙法の選挙権年齢や憲法改正のための国民投票の投票権年齢が18歳と定められるなど、国政上の重要な事項の判断に18歳や19歳の方々であっても参加する方向での政策が進めてこられました。
このような流れを受けて、私人間の取引や生活に関する民法においても18歳以上の人を大人と取り扱うのが適当ではないかとの議論の下、18歳を成年年齢とする世界的な流れを受けて、民法上の成年年齢も20歳から18歳へと改正されました。
18歳から成年(大人)として扱われることになることで、より早くから親の同意なく自分だけで契約をすることができるようになりました。
(参考:https://www.moj.go.jp/content/001300586.pdf)
一方で、少年法上の「少年」は「20歳に満たない者」とされ、犯罪を起こしてしまった少年は、少年法に定められた特別な手続である少年審判を経て、保護処分という刑罰とは異なる処分を受けることになっています。
では、民法上の成年年齢が変わった際に、刑事事件・刑事裁判との関係でも成年年齢は変わったのでしょうか。
民法上の成年年齢の引下げ後においても、少年法上の少年は、「20歳に満たない者」としており、現在もなお平成30年民法改正以前と変わらない基準を維持しています。
これは、少年法が特別な考え方をもっているためです。
では、そもそも少年事件における手続はどのような流れになるのでしょうか。
捜査段階の手続
警察や検察官が捜査をする段階では、少年事件の場合であっても、基本的な流れは成人の事件と変わりません。
成人の事件の場合と同様に、逮捕された後に証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合、勾留という身体拘束を受けることになります。
ただ、少年事件の場合、この勾留の代わりに少年鑑別所で身体拘束を受けるという勾留に代わる観護措置となる可能性があります。
身体拘束を受ける点では、勾留と勾留に代わる観護措置に違いはありませんが、成人の場合と同じ勾留は10日間の身体拘束の後にさらに最大10日間身体拘束を受ける可能性があるのに対し、勾留に代わる観護措置の場合は10日までになっています。
通常の刑事事件においては、検察官は最終的に事件の内容や軽重を踏まえて起訴不起訴の判断をすることになりますが、少年の事件の場合は、犯罪の嫌疑があればどんな軽微な事件でも家庭裁判所に送致しなければなりません。
これを、家庭裁判所送致といいます。
家庭裁判所での手続
少年事件の場合、裁判所から言い渡されるものは「保護処分」というものです。
「保護処分」は、罰金や懲役などの「刑罰」とは異なり、少年の健全育成を目指し、少年の更生を図るためのものになります。
非行をしてしまった少年が再び非行をしてしまうのを防ぐためには、少年の考え方を正したり、少年の周辺環境を整えたりすることが重要であるとの考えを少年法が持っているからです。
そのため、家庭裁判所においては、そもそも犯罪が成立するのかといった審査に加えて、家庭裁判所調査官や裁判官による様々な教育的な働きかけがなされます。
家庭裁判所調査官は、少年が犯罪を起こした原因はどこにあるのか、少年の家庭環境や交友関係に問題はあるのか、少年の資質や考え方の特徴等を様々な面から調査をします。
その後、家庭裁判所調査官は、少年調査票というものを作成し、審判をする裁判官に家庭裁判所調査官の考える処分の意見を述べます。
そして、家庭裁判所の裁判官は、上記調査の結果を踏まえて少年審判を開くかどうかを考え、審判を開くという判断をしたときには少年や保護者の考えを聞いたのち、処分を下すことになります。
家庭裁判所での処分
裁判官が最終的にする処分には、①審判不開始、②不処分、③保護処分、④検察官送致、⑤知事又は児童相談所長送致の5種類があります。
①審判不開始や②不処分の判断は、そもそも非行事実が認められない場合だけでなく、非行事実はある場合であっても、調査の過程で行われた教育的な働きかけ等によって、少年の問題性が解消し、少年が再び非行をするおそれがないと認められた場合にもなされることがあります。
次に、③保護処分には、ⅰ保護観察、ⅱ児童自立支援施設または児童養護施設送致、ⅲ少年院送致の3種類があります。保護観察とは、1月に1、2回程度の頻度で保護観察官や保護司の下へ通いながら、指導監督を受けていくという処分になります。一方で、少年院送致は、文字通り少年院の中で規則正しい生活を送りながら様々な教育を受ける処分です。
④検察官送致は、「検察官逆送」「逆送」などとも呼ばれ、刑事処分が相当であると判断される場合、検察官のもとに事件の記録を送り返すというものです。これは、殺人や傷害致死などの一定の重大事件を起こしてしまった場合に下される処分になります。成人と同じ裁判を受けることになるため、有罪となれば前科がついてしまうことになります。
最後に
少年事件では、犯罪の成立を争わないとしても、今後同じような非行をしないためにも、少年に対する教育的な働きかけが重要な場合は少なくありません。
もし子供が犯罪をしてしまったことについてお悩みの方がいましたら、ぜひ新宿清水法律事務所にご相談ください。